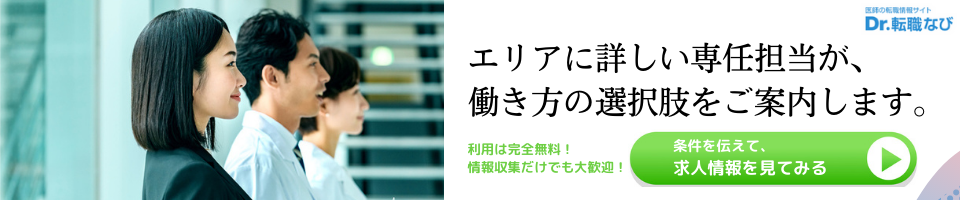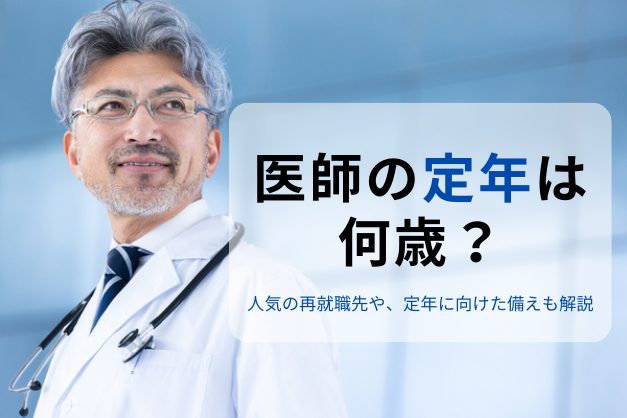
医師に定年はなく、開業医やフリーランスは自らの判断で働き続けられます。一方で公立病院勤務医は65歳が定年で、再雇用制度で70歳まで働ける場合も多いです。民間病院では60歳または65歳で定年が一般的ですが、働く意志があれば再雇用制度を利用できます。定年後は常勤や非常勤としての選択肢があり、早期にキャリアプランを考えることが重要です。
本記事では、医師が定年となる年齢や医師の定年後の働き方、定年後のキャリアプランにまつわる不安の解決法について解説します。
医師が「定年」となる年齢は?
医師免許は、年齢によって失効することはありません。
そのため医師という職業自体に定年はないものの、医師の定年退職制度の有無は勤務先や働き方により異なります。
開業医・フリーランスの医師には、定年がない
開業している医師や、常勤先を持たず非常勤として医療機関と契約して働くフリーランス医には、定年はありません。
自分自身が引退を決めるまで、医師としてのキャリアを継続することが可能です。
勤務医の場合は、勤務先によって制度や年齢が異なる
医療機関と雇用契約を結んで働く勤務医の場合は、勤務先によって定年制度の有無や内容が異なります。
国公立病院で働く公務員医師の場合、定年は65歳
国公立系の大学病院や公的病院・国公立病院機構の病院で働く医師は、給与・待遇や福利厚生が公務員に準ずる「みなし公務員」として位置づけになっています。
そのため、国家公務員法で定められている65歳が定年となります。
参照:国立病院機構「医師の処遇 2023年度版」
定年後5年間の継続雇用制度のある病院も多くみられ、その場合は65歳の5年後である70歳まで働くことができます。
この再雇用制度をとる場合、定年退職後の再就職で定年前の70%の年収が保障されています。また70歳まで勤務することで、5年分の退職金を受け取ることもできます。
再雇用制度を利用しない場合には、65歳に達する前に民間病院へ転職して働き続ける医師が多いようです。
▼関連記事
民間病院の勤務医は、60歳や65歳で定年となるケースが多い
民間病院で働く医師の定年制度は各医療機関の就業規則で定められており、施設ごとに内容も大きく異なります。
定年制度がない医療機関も一部ありますが、一般的には60歳や65歳で定年退職となる制度が設けられた医療機関が大半です。
ただし病院長や副院長などの職位に就く医師は定年後も病院運営に携わる等、例外として定年延長が認められている場合もあります。
また病院幹部でなくとも医師自身に働く意思があれば、「再雇用制度」や「継続雇用制度」等を利用して65歳を以降も働くことができる医療機関も少なくありません。
このように医師は60歳を超えても活躍の場が非常に多い職種といえるものの、民間病院の場合は病院ごとに規定が大きく異なります。
勤務医として働いている場合には、自分が働く医療機関の定年制度の内容を確認した上で、早めに定年後の働き方を見据えたキャリアプランを検討しておくと安心です。
ご自身の「定年後の選択肢」を検討してみませんか?
定年を迎えた医師の代表的なキャリアプランとは?

60代になると、体力の低下等の問題が生じやすくなります。
これまでと同様の働き方が困難になってしまった場合を想定して、定年後はどのような働き方をするのか事前に検討しておくことが重要です。
以下では、定年を迎えた医師の代表的なキャリアパスをご紹介します。
心身にかかる負担やプライベートとのバランスも考慮しながら、どのような働き方や仕事内容・勤務先が最適なのか考えていきましょう。
①常勤で働く
常勤という働き方は勤務時間が一定で、安定期な収入が得られる点が大きな魅力です。
ただし、60歳以降も以前と同等のパフォーマンスを発揮し続けることは困難でしょう。
そのため、業務内容を変更する等の配慮も必要になります。
特に外科系を専門とする医師の場合は、手術なしで外来や病棟管理に専念できる仕事や、内科系の専門へ転科等、セカンドキャリアを検討することが求められます。
内科系を専門とする場合も、比較的おだやかな労働環境で働ける以下のような施設における求人を検討する医師が多くなっています。
介護老人保健施設で、施設長として働く
要介護者の自立支援を目的とした施設である介護老人保健施設で働く医師は、主に入所患者の健康管理や健康指導を行うことが業務となります。
夜間のお看取りやオンコールは常勤医が担当する場合もありますが、常勤医の負担軽減のため非常勤医師が担当するという施設もあります。
病院や診療所等で働く場合と比べて心身の負担が少ない働き方が実現しやすいことから、定年前後の医師から人気が高い勤務先となっています。
ただし、求人数はそれほど多くありません。
募集が出るとすぐに枠が埋まってしまうケースも珍しくないため、勤務を希望する場合にはこまめな情報収集が重要になります。
療養型病院で、常勤医師として働く
症状が安定している慢性期の患者へ長期的な医療・リハビリ等を提供する療養型病院も、定年前後の医師が選択するセカンドキャリア先として、代表的な施設です。
60歳以上のベテラン医師も歓迎される傾向があり、当直なし勤務や週4日勤務の相談ができる病院も多くあります。
ワークライフバランスを重視しながら常勤医としてのキャリアを継続したい医師にとって、希望の働き方を実現しやすい勤務先といえるでしょう。
②非常勤で働く
常勤先の医療機関を持たずに非常勤として働く「フリーランスへの転向」も、定年を迎えた医師の代表的な働き方です。
非常勤として働く最大のメリットは、自身の都合や体力に応じて働く回数や時間を自由に調整できることです。
例えば「週3回の日勤(朝から夕方まで)で働く」「週5回、午前中のみ働く」等、複数の勤務を組み合わせて柔軟な働き方を実現できます。
健診アルバイトで、非常勤医師として働く
健診業務の専従医として、健診センターや病院・診療所、企業や学校などの巡回先で健診業務に携わります。
業務内容は主に健康な方を対象に、問診や聴打診を行うという案件が大半です。
心身の負担が少ない医師のアルバイトとして高い人気があり、春や秋といった入学や入職の多い時期には、例年スポットアルバイトで多くの募集が出ています。
求人数の多さから条件に合う案件を見つけやすいという利点がある一方で、場合によっては毎回異なる勤務先に赴いて働くケースもあります。
このような場合は、定年前後の医師にとって負担のある働き方となってしまうかもしれません。
一方 定期非常勤として働く場合は、勤務曜日や時間・場所は基本的に固定されます。
よって、勤務スケジュールを都度調整する必要もなく、毎回同じ診療環境のもと落ち着いて勤務できるでしょう。
加えて安定的な収入を確保することもできるため、定年後の医師により適した働き方といえます。
▼関連記事
外来診療のアルバイトで、非常勤医師として働く
豊富な診療経験や患者との円滑なコミュニケーションが求められる外来医療の現場でも、多くのベテラン医師が活躍しています。
外来アルバイトで最も求人数が多いのは、一般内科外来です。
幅広い症状・疾患を対象に診察や処方を行うことが業務内容となるため、これまでの経験やスキルを存分に活かせるアルバイトといえるでしょう。
午前のみ・午後のみといった数時間から勤務できる案件や、朝から夕方まで働く終日勤務の案件など、様々な勤務条件で募集が出ています。
その他、消化器内科外来や循環器内科外来、整形外科外来など、特定の診療科の患者が受診する専門外来の案件もあります。
いずれの外来アルバイトにおいても、今までの臨床経験に基づいて「即戦力」となってくれる医師が求められています。
定年後の医師の年収と、将来に備えた対策

働き方や仕事内容の変化から、年収が下がる可能性が高い
上述のように医師は定年を迎えるもしくは60歳を超えるタイミング等で、従来とは異なる雇用形態や仕事内容を選択して働くケースが大半です。
このような働き方の変化に伴って、収入が減少することも考えられます。
例えば 定年退職をした後は年金のみを収入源とする場合、65歳以降に受け取れる金額は月あたり220,496円となっています(※)。
(※)平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)43.9万円)で40年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準。
参照:日本年金機構「令和3年4月分からの年金額等について」
定年後の医師が受け取れる年金は、思っている以上に多くありません。
高年収というイメージのある医師という職種であっても、貯金などの資産を切り崩したり、定年後も引き続き働いたりしていかなければ、これまで通りの経済感覚で暮らすことは難しくなるでしょう。
定年後の働き方も視野に入れて、早めにキャリアプランを立てよう
医師という職業自体に定年はなく、60歳を超えても活躍できる場は多くあります。
将来も無理なく、医師としてのキャリアプランを継続したいと考える場合には、セカンドキャリアに備えて早い段階から準備を進めておくことをおすすめします。
定年世代を迎える前に「医師として、どのような医療に携わりたいのか」「どのような医師でありたいのか」といったことを考えながら、様々な選択肢を検討していきましょう。
特に、定年後も常勤医師として長く働き続けたいと考える場合には50代のうちから情報収集を始めておくと良いでしょう。
定年間近になって慌てることなく最適なキャリアを選択できるよう、自身が希望する働き方を実現できる医療機関の目星をつけていけると安心です。
▼関連記事
定年以降のキャリア設計は、医師専門の転職エージェントに相談を
なお定年前後の医師を対象とする求人は、一般的な求人サイトでは見つけにくい傾向があります。
効率的に情報収集を行いたいと考える場合には、医師を専門とした転職エージェントの活用を検討してみるのも一つの方法です。
コンサルタントに希望条件を伝えるだけで、理想とする老後の働き方を実現できる医療機関に関する情報提供を受けられます。
また、定年後のキャリアプランを立てるにあたって迷いがある場合にも、これまでの医師転職サポートの経験から得た知見を活かしたアドバイスを得ることも可能です。
定年後や60歳以降のキャリアに関する不安やお困りごとがある先生は、ぜひこの機会に「Dr.転職なび」のコンサルタントまでご相談ください。