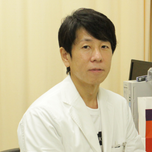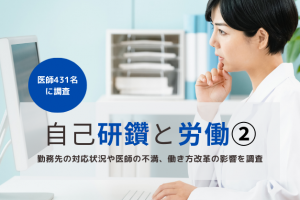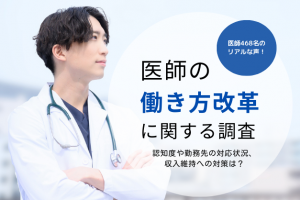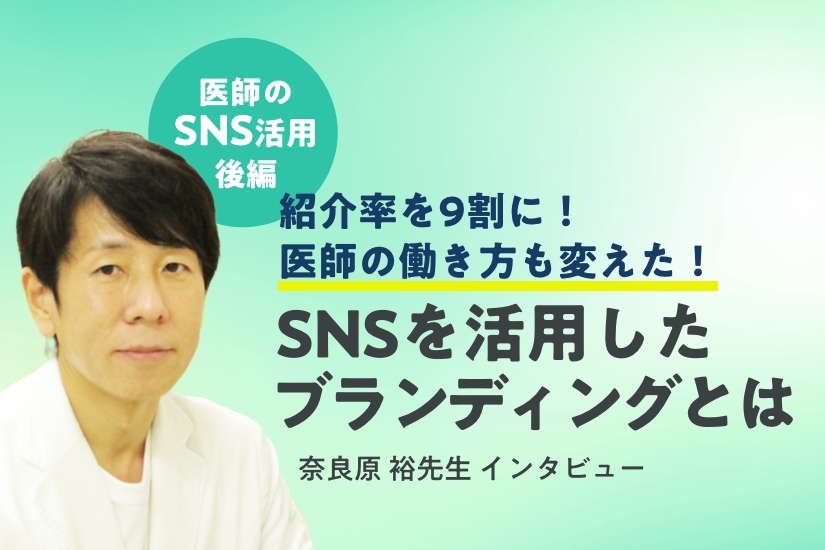
前編・後編でお届けしている奈良原 裕医師へのインタビュー。
前編では、多くの「いいね!」を獲得したFacebookページ制作のきっかけや経緯、医師として患者様へ情報を発信するための独自の取り組みや思いを伺いました。
後編となる本記事では、SNSを活用した自科のブランディング、そしてブランディングの成功によって成し遂げた患者構造の改革や医師の働き方の変化についてお聞きします。
奈良原 裕(ならはら ゆたか)
1970年生まれ、東京都出身。中央大学法学部法律学科を卒業後、石油元売りメーカーに入社したが「直接相手に喜んでもらえる仕事をしたい」との思いから、およそ5年勤務した同社を退職。医師を目指し1年半の受験期間を経て、高知大学医学部へ再入学。卒業後は外科・高度救命救急を学んだのち、38歳で心臓血管外科医となる。
現在は神奈川県横浜市の菊名記念病院にて心臓手術の執刀をしながら、北海道をはじめとする地域医療にも携わり、地域医療の新しい未来モデル作りにも挑戦している。
「ブランディング」によって得られたメリットとは?
自科の「ブランディング」に繋がる取り組みの一つとして、SNSを活用
Q:SNSを活用した「ブランディング」とは、どのような取り組みなのでしょうか?
「今でこそ<病院マーケティング>という言葉を耳にする機会も増えましたが、モノを売るという商売ではない医療機関で働く人々にとって、これまでマーケティングという存在は縁遠いものだったと思います。
しかしこれからの時代は、そうは言っていられません。
医療機関であっても、生き残りをかけて戦うことを余儀なくされる時代になっていると思います。
そのため、今後医療機関におけるマーケティングの重要性は一層高まってくるであろうと考えています。
私たちの診療科では患者様のデータを集計し詳細に分析するといった手法でマーケティングを行っていますが、それと同時に自分たちのブランディングにも力を入れています。
FacebookなどのSNSを活用して情報を発信することも、このブランディングの一環と考えています。」
SNS活用によって、患者様の紹介件数や関係構築にも好影響が
Q:SNSを活用したブランディングによって、集患や患者様との関係性にどのような影響がありましたか?
「最も多いのは、SNS上で繋がった先生方が患者様をご紹介してくださるケースです。
SNSの投稿を見て、私たちに対して親近感や信頼感を持ってくださった先生方が、ご自身の患者様に『こういう先生たちがいるから、一度話を聞きに行ってみませんか?』と紹介してくださる。
その患者様が実際に私たちの外来を受診してくださって、心臓手術に繋がるという形です。
それから、患者様やご家族との関係構築がよりスムーズになると感じることも多いですね。
患者様やご家族が診察室に入って来られるときに『先生のFacebookを見ました!』『Instagramのあの投稿、見ました!』といったことが会話のきっかけになることもよくあります。
患者様やご家族は、SNSで私のことをある程度知ってくださっている状態なので、信頼感を築いていく過程がより早く、円滑に進むように思います。
SNSで自分たちのことを知ってもらうということは、患者様との関係構築において非常に有益だと思います。」
「救急対応中心」の患者構造から、「紹介率9割以上」に変化
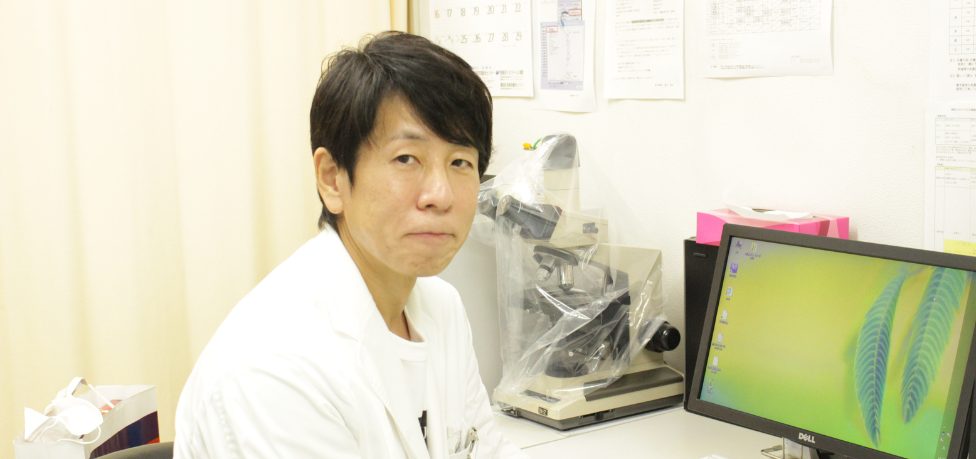
Q:その他には、どのような影響がありましたか?
「まず、現在と10数年前では、患者様の構造が大きく変わりました。
以前は、救急患者様の緊急手術に頼っていた部分が大きくありました。
そうすると、今この瞬間にも救急車で患者様が来院して緊急手術になるかもしれず、その日のスケジュールがすべて変わってしまう。
長い間、このような働き方を続けていました。
その当時、救急患者様の割合は全体の半数以上を占めていましたが、現在はなんと1割を切っています。
9割以上が紹介患者様という患者構造に変わり、トータルの患者数も伸ばすこともできています。
このお話をすると、「救急の患者様の受け入れを、断っているのですか?」と聞かれることがあるのですが、現在も救急患者様の対応も行っています。
ただ、緊急手術の件数は以前より減っています。
昨今では病院も生き残りを懸けた時代に入っていて、数年前までは緊急や救急の患者様を受け入れていなかった大規模病院でも、救急を積極的に受け入れる方針に転換したというケースも増えています。
いわゆる<救急の奪い合い>の結果、今までうちの病院に集中していた救急患者様が分散し、私たちが担当する救急患者様は以前より減少している、という状況です。
ただ私たち心臓血管外科では、周りの先生方が安心して患者様を紹介してくださるような関係構築を目指してブランディングを続けてきていました。
そのため患者構造の大部分を占めていた救急患者様が減っても、多くの紹介患者様のおかけで 患者数が激減するような状況に陥らずに済みました。
このような患者構造の改革を実現できたのは、SNSをはじめとするブランディング活動を通じて、患者様やご家族、そして紹介元となってくださる医師の方々が、私たちに信頼を寄せてくださったからだと考えています。」
患者構造の変化によって、医師の「働き方」も大きく変わった
「患者構造が大きく変わったことで、私たち医師の働き方にも大きな変化がありました。
昼夜を問わず飛び込んでくる救急患者様と違って、紹介患者様の場合は予定を組んで手術を行うことができます。
それに伴って、執刀する私たち医師の働き方も 予測不能なものから、ある程度見通しを立てて生活できる働き方へ変わりました。
このことは、2024年から施行される<医師の働き方改革>にも繋がっていく、大きな意味を持つ取り組みになったと思います。
また、心臓血管外科としてのブランディングや患者構造の改革を実現できたことによって、医師の体制を増強することもできました。
以前は2名だったところが今は4名体制となり、医師一人あたりの業務負担の軽減や、残業時間の減少に繋げることができています。」
医師がSNSを活用するために知っておきたいこと

SNSを活用したブランディングによって、救急中心となっていた患者構造を変え、医師の働き方も大きく向上させてきた奈良原医師。
最後に、医師がSNSを利用する際に配慮したいポイントを伺いました。
見る人に「不誠実さ」を感じさせない配慮が大切
「SNSでは、どのような情報をどの程度出すかのバランスが非常に難しいのですが、情報を発信する側は特に意識すべき点だと思います。
投稿では、仕事に関する情報もさながら、自身のプライベートも表出させることが多くなります。
そのため、見る方に「不誠実」という印象を持たれてしまうことのないような配慮は重要です。
文章や写真はもちろんですが、投稿のタイミングや頻度にも注意したいところです。
例えば、医師が飲み会で酔っ払ってカラオケで歌っている写真投稿を見て、手術を控えた患者様がその医師を信頼できるのか?といったら、そうではないかもしれません。
かといって、真面目すぎる少しの隙も見せないような投稿もあまり良くないとも思います。
いかにも広告宣伝目的というようなものや、良い面しか見せないような内容になってしまうと、親しみを持ってくださるような要素がなくなってしまいます。
また写真投稿の際には、画像の細部まで拡大しながら入念にチェックするようにしています。
例えば、手術室の写真を投稿する場合。
点滴ボトルに書かれている名前も、厳守すべき患者様の個人情報に該当しますので、画像加工を施してから投稿をします。
投稿を見る方は、友人や知人でもない その切り取られた一瞬一瞬しか知らない方である可能性も大いにあります。
そのためSNSに投稿する際には、誰が見ても「不誠実」という印象を持つことがない内容や頻度、タイミングなどを考えるようにしています。」
SNS投稿では、見えない相手にも配慮するバランス感覚が求められる
「また、<これは投稿しても大丈夫><これは投稿するべきではない>といった線引きができるバランス感覚も、医師としてSNSを利用する上では大切なことだと思います。
相手との関係性を鋭敏に察して、親友ならどう思うか、知人ならどう思うか、赤の他人であればどう思うか。
たとえ同じ内容を投げかけた場合でも、相手によって受け取り方はそれぞれ違いますよね。」
Q:見えない相手にも配慮するためには、どのような方法があるのでしょうか?
「SNSには、FacebookやTwitter、Instagramなど多くの種類があり、それぞれの特徴も異なります。
これらのSNSツールを使い分けることも、見えない相手への配慮という点で効果的かもしれません。
人によって捉え方が違う部分もあるとは思いますが、各SNSツールで大きく異なっているのはフォロワーの属性だと思います。
※フォロワー…SNSで投稿を見ることができるよう登録をしてくれた人のこと。
私の場合は友人など、リアルでも親しみが強い繋がりを持つフォロワーが多いのがInstagramです。
医師などのビジネスでの繋がりを持つフォロワーが多いのがFacebook、私個人のキャリアに興味をもってくれたフォロワーが多いのがTwitterという感じです。
このように各SNSのフォロワーの属性の違いを踏まえてみると、投稿する内容や伝え方もそれぞれ違ったものになりますよね。
関連して、投稿を見た人が「またこの記事か…(他のSNSツールでも同じ記事を見た)」となってしまうような事態を避けるために、同じ記事を複数のSNSに投稿することは極力避けるようにしています。
こちらからは見えない相手であっても、ツールや内容・伝え方を使い分けることで、相手が受け取る印象を少しでも良いものにできればと考えています。」
SNS活用では、自分自身が「楽しむ」ことも重要

Q:本日は貴重なお話をありがとうございました!
最後に、今後さらにSNSを活用したいと考える医師の方々へメッセージをお願いします。
「SNSは、多くの人と繋がり、自分に興味を持ってくれた人がより深く自分のことを知ってくれるための重要なツールだと考えています。
その相手が医師の場合には、有益な情報交換ができたり、コミュニケーションをより深めることができたり、さらには患者様の紹介に繋がるケースもあるかもしれません。
相手が患者様やそのご家族であれば、実際に受診や手術などに繋がったり、関係構築や信頼感の醸成をスムーズにしてくれたりといったことも期待できると思います。
何のためにSNSを利用したいのか、ということはよく言われることかと思います。
開業医の先生であれば、自分のクリニックへ集患するということが目的になるのかもしれません。
集患することで、ご自身の経済的な利益にもつながりますよね。
私の場合は、SNSを活用することによって仲間を増やし、心臓血管外科のブランディング活動をさらに確立していきたかった。
その結果、救急対応中心であった患者構造を大きく変えることができ、医師としての働き方にも非常に良い影響がありました。
医師に限ったことではありませんが、SNSを活用するためには、何より<自分が楽しめるかどうか>が大切だと、個人的には感じています。
本人が楽しんでいないSNSの投稿は、見ている側に意外と伝わってしまうものです。
SNSを投稿することへの強制感や義務感が見え隠れしていると、かえって逆効果にすらなってしまうと思います。
そのようなときには、ご自身がSNSを活用したいと思った目的に一度立ち返ってみることも、有効かもしれません。」
▼関連記事はこちら▼