
日本屈指の乳がん治療の名医として知られている山内英子氏が診るのは、患者の身体に巣食う病気だけではない。愛と感謝の念を抱き、病を心ごと診るのが彼女流だ。
幼少期から医師をめざし、初の女性外科研修医から初の外科チーフ・レジデントになるも妊娠・出産により離脱。その後も、何度も挫けそうになった彼女を支え、前へと向かわせた原動力とは?
※編集部より:本記事はエムステージ運営「joy.net」から、特に注目度の高かった記事をピックアップしてお伝えしています。
山内英子(やまうち ひでこ)先生
聖路加国際病院副院長、ブレストセンター長、乳腺外科部長。1963年東京都生まれ。
87年順天堂大学医学部卒。聖路加国際病院外科レジデントを経て、94年渡米。
ハーバード大学ダナファーバー癌研究所、ジョージタウン大学ロンバーデイ癌研究所でリサーチフェローおよびインストラクター。
ハワイ大学外科レジデント、外科集中治療学臨床フエロー、南フロリダ大学モフイツトキヤンサーセンター臨床フエローを歴任。
2009年聖路加国際病院乳腺外科医長、10年よりブレストセンター長、乳腺外科部長、2017年より聖路加国際病院副院長。
「患者に寄り添う外科医へ」聖路加初の女性外科研修医となる
「大きくなったらお医者さんになる。」
青森県で病院を経営していた外科医の叔父に憧れ、幼い頃から医師志望だった山内英子氏が10代でめざしたのは「精神科医」だった。
「中学生の時、父が双極性障害を罹ったのです。
父は自分で会社をやっていたのですが、一旦寝込むと起きられなくなるんですよ。
大好きな父が苦しんでいる姿を身近で見ていて、なんとか治せるようになりたいと思いました」
少女だった山内氏に衝撃を与えたのは、映画『カッコーの巣の上で』だった。
名優ジャック・ニコルソン演じる主人公は、刑務所での労役を逃れるため、精神疾患を装ってまんまと精神病院に移る。
人権を侵害するような「治療」を受けている入院患者たちとの間に友情が芽生えた主人公は、彼等を誘って反抗や脱走を企てるが、最終的には“危険な患者”としてロボトミー手術(脳の一部を破壊・切除する手術)を施され、廃人と化す。
「心を動かされました。
凄く辛くて、ああいう状況を変えるためにも精神科医になりたかったのですが、大学で学ぶうちに『私には無理かな』と。
当時の精神医療は薬物療法が中心で、カウンセリングもなく、患者さんに寄り添うという私が理想とする医療とは異なっていたのです」
思い迷っていた大学5年生の春休み、進路を決定づける出来事が起こる。
「聖路加国際病院に見学行き、西尾剛毅(にしおたけき)先生の外科手術を見せていただいたのです。
そこで、癌などの疾患を抱えていた患者さんが手術を受け、元気になって新しい人生へと歩み出して行く姿を目の当たりにして、外科医になろう、西尾先生の弟子になろうと決心しました」
だが大きな壁が立ちはだかっていた。
聖路加国際病院では、女性の外科研修医を受け入れていなかったのだ。
「当時は聖路加に限らず、女性の外科医は少ない時代。
順天堂の同期でも、外科に進んだ女性は私だけでした。
だけどどうしても入りたくて、『性別ではなく、選抜試験の成績で判断してください』と直訴し、猛勉強の末、採用してもらいました」
チーフ・レジデント昇格直後まさかの妊娠発覚
聖路加初の女性外科研修医として働き始めた山内氏。
「『やっぱり女の子はダメ』と言われないように頑張っていた面はありましたね。
ただ、『男性に負けてたまるか』みたいな片意地張るのは好きじゃないので、ごく自然に…です。
研修医はみんな、回診時に上の先生から能力不足を叱責され、厳しい指導を受けるのですが、その際『あの子は女だからきっと泣くだろう』なんて思われていたみたいです。
昔は、そういう時代でした。絶対泣きませんよ(笑)。
そのこと以外は、体力的にもハンデは感じませんでした。
何より、一緒に働いていた看護師さんとかがすごくサポートしてくれたのが、ありがたかったですね」
世の中には、女性の外科医を不安視し、拒否する患者もいると聞くが、風当たりはどうだったのだろう。
「そういうことはなかったですね。
逆に乳房から痔まで、『女医さんがいい』という女性患者さんは少なくありませんでした。
中でも多かったのが乳がんの患者さんだったので、ブレストセンターを立ち上げようという話が持ちあがったほどです。
初代ブレストセンター長の中村清吾先生は、私が1年目の時に5年目で、手取り足取り指導してもらった間柄です」
やがて努力が認められ、女性で初めて外科のチーフ・レジデントに就任。
結婚3年目だったものの子宝には恵まれていなかった山内氏は、バリバリキャリアを磨いて行こうと張り切っていた。
そんな矢先、衝撃の事実が発覚する。妊娠していたのだ。
「本当にびっくりしました。
周囲からは、チーフはもう無理だから辞めなさいと説得されたのですが、私はせっかくチーフになれたのだから、何が何でも頑張ろうとしました。
でも、切迫流産になり自宅で絶対安静を言い渡されて。
泣く泣く、チーフの座を後輩の男性に代わってもらいました。
今となっては、正しい決断でした。
その後は、二人目には恵まれませんでしたし、私自身母親になって、たくさん学ぶことができました。子宮にへばりついていてくれた息子に感謝しています。
お子さんがいる乳がんの患者さんの想いによりも、より共感できるようになったかもしれません。
周囲には、大変な迷惑をかけて、『伝説のチーフ・レジデント』なんて言われていますが、そこは後進をサポートすることで恩返ししたいと思っています」
▼関連記事
こうして1年の産休に入った山内氏だったが、産休明け間近、かねてよりアメリカで腫瘍内科のトレーニングを受けたいと希望していた夫(聖路加国際病院腫瘍内科部長)のアメリカ留学が決まる。
夫の夢を応援すべく、臨床の場への復帰を諦め、彼女は1歳の息子を連れて渡米した。
渡米後、子育てに奮闘しながら乳腺外科への道へ
人生万事塞翁が馬。
自分のキャリアを諦めて渡ったアメリカで、山内氏は、現在の仕事に繋がる乳腺外科の道を歩み始める。
「夫が勧めてくれたハーバード大学のカンファレンスがきっかけで、それまでは経験のなかったリサーチという分野で乳がんとかかわり始めたのです」
その頃、アメリカは乳がん患者が爆発的に増え、社会的な関心も高かった。
当然、治療法も社会の体制も進歩する。
そんな最中に身を置くことで山内氏は、最先端の研究に加え、アメリカの医師資格を取得して乳腺外科医の臨床も十分に積み、聖路加のブレストセンターへの凱旋を果たしたのだった。
とはいえ、アメリカでの日々は決して順風満帆ではなかった。
特に夫婦そろってハワイ大学の研修医になり、3日に一度の当直と週100時間の勤務をこなしていた頃の子育てには苦労した。
「アメリカでは子どもを一人で留守番させるのは虐待になるので、主人の両親が鹿児島から、息子の面倒を見に3カ月の予定で来てくれたことがありました。
ですがある晩、私の帰りを待ちわびて玄関から動こうとしない息子の姿を見て不憫に感じた義母が激怒したのです。
『英子さん仕事を辞めなさい。私たちは日本に帰ります』と。
さらに息子には、『将来、あなたは絶対仕事をしている女性とは結婚しなさんな』って。
そしたら主人が『英子は僕の夢をサポートするために日本で一度メスを置いた。もし、彼女に、育児のためにうちにいろというのなら、僕が仕事を辞める』と言い出したんです。
結局ご両親は、1週間で帰国してしまいました」
その後山内氏は、実の両親、息子の同級生の母親、実父の親友など、様々な人々の助けを借りて、無事、研修を修了。
日本では断念した、チーフ・レジデントのポジションも務めた。
「チーフ終了のパーティでは、その後理解してくれ、サポートしてくれた主人の両親もお招きし、大勢の方々に助けてもらえたことを感謝するとスピーチしました。
私は本当に、恵まれていると思っています」
そんな山内医師も、帰国したての頃は、日米の違いに愕然としたという。
「たとえばアメリカでは、乳房全摘と同時に再建手術を行うのが普通でしたが、日本ではまだ、インンプラントによる再建手術は保険適応外でした。
遺伝性乳がんの検査は、未だに保険外で自己負担ですよね。
なんでもアメリカ流が優れているとは思いませんが、せめてアメリカの女性が得られるベネフィットは、日本の女性も得られるようにしたい。
そのために私がやるべきことは沢山あると思いました」
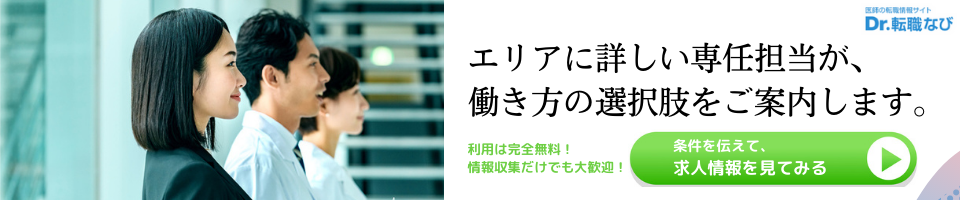
患者様の「自分らしさ」をサポートする医療
以来今日まで、山内氏は厚生労働省研究班での活動など、病院内外で精力的に行動し、着実に、日本の乳がん医療を進化させてきた。
「患者さんの後ろに見え隠れしている “悩み”というボールを拾うのが私の役割です。
一個も落としたくない。
そのためにも、人を人として診て行かなくてはいけないと思うのです。
身体と心は通じていますから。」
乳がんは今や「不治の病」から「慢性疾患」へと移行しつつある。
10年生存率の平均は80~90%を超え、患者には、治療後も長い人生が待っているにもかかわらず、自分自身を「がん患者らしく」という枠組みにあてはめようと苦悩している女性はあまりにも多い。
そこで取り組みを始めたのが、乳がん患者が「自分らしく」歩むのをサポートする「“リング”プログラム」だ。
患者が抱える多様な悩みに対し、連続した講座を開催し、患者同士の繋がりに加え、医療従事者の他、関連する分野の専門家が参加して、問題解決をめざす。
「たとえば、治療と仕事を両立するための『就労Ring』では、5~10人ぐらいの患者さんが集まって、仕事を通して経験する問題について話し合ったり、社会保険労務士さんに就業規則や休業手当の相談をしたり、ハローワークの職員を交えて、再就職活動の際の経験談を語りあったりします」
最初は、若年性乳がんの患者さんのための「Pink Ring」から始まったこの取り組みも、回を重ねるごとに発展し、「Smile Ring」「就労Ring」「Beauty Ring」「リフレRing」「シェイプアップRing」、「おさいふRing」(がん治療とお金の問題や人生プランを考える)、「ママキャン Ring」(子育てしながらの、がん治療を考える)という8種類ものプログラムに増えた。
院内のプログラムではあるが、聖路加の患者以外の参加も歓迎している。
「もちろん、拾ったボールを私一人で抱えることはできません。
それで『誰か、お願い』と声をあげると、うちのチームは皆、積極的に立候補してくれます。
心から、感謝しています」
まさに患者に寄り添い、愛を持って、心も一緒に診る医療の実践。
聖路加プレストセンターのスタッフは、山内氏と同じ目標を見ている。
※内容は取材当時(2017年4月)のものです。

▼合わせて読みたい関連記事







